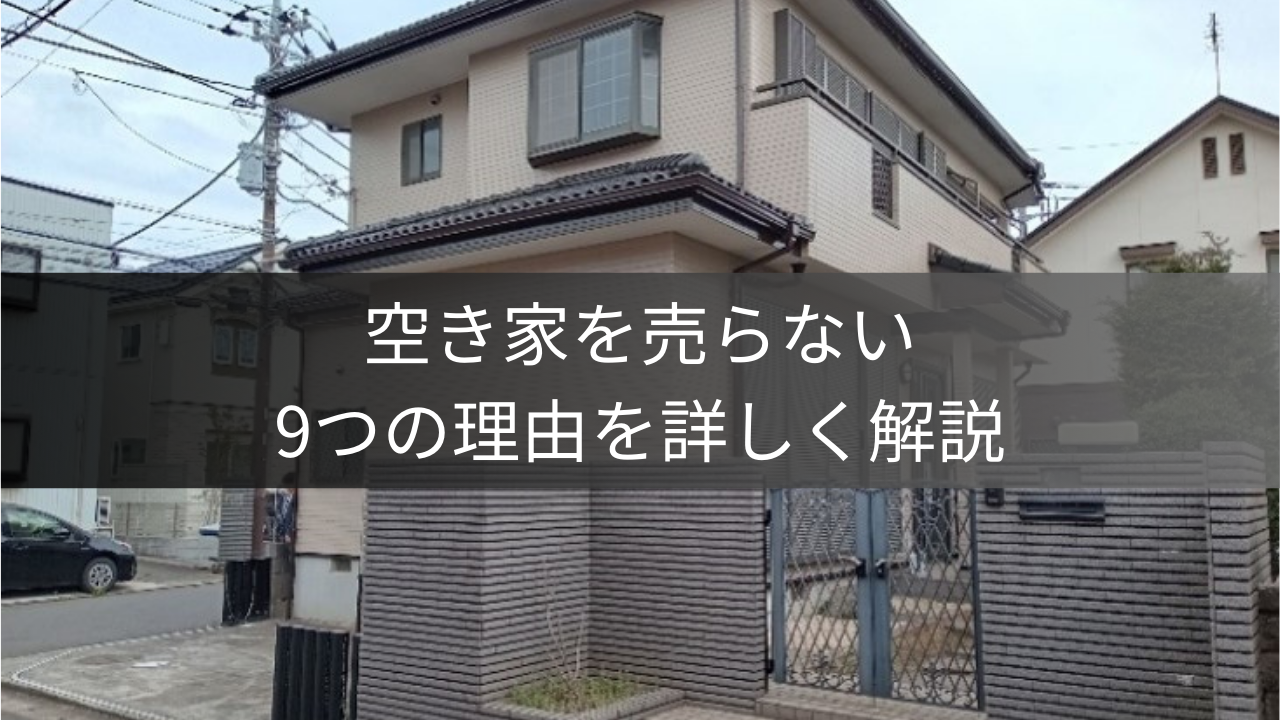空き家を国に返すことはできる?相続土地国庫帰属制度の落とし穴と後悔しない処分方法とは

実は今、「いらない土地は国に返せるらしい」という情報が広まりつつあり、空き家を所有して困っている人たちの間で話題になっています。
その背景にあるのが、2023年から始まった「相続土地国庫帰属制度」という新制度。
名前を初めて聞く人も多いかもしれませんが、この制度をうまく使えば、一定の条件のもとで不要な土地を手放せます。
この制度ですが、「空き家があれば誰でも簡単に国に返せる」とは限りません。
実際には、建物を解体して更地にする必要があったり、申請できる土地に厳しい条件があったりと、知らなければ損するポイントがたくさんあります。
この記事では、「空き家を国に返す」選択肢が本当に現実的なのか、制度の仕組みと注意点をわかりやすく解説。
さらに、制度を使えない場合の売却や寄附といった代替手段も具体的にご紹介します。
目次
相続土地国庫帰属制度とは

「空き家を国に返す」
それは、管理や維持に悩む多くの相続人にとって、切実かつ現実的な願いかもしれません。
特に、使い道のない土地や遠方にある空き家を相続した場合、その手間と費用は決して小さくありません。
こうした背景から、2023年4月に施行されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
空き家を国に返すニーズの高まりと制度創設の背景
少子高齢化が進む日本では、親から相続したものの使い道がなく、維持費や管理負担だけが増えていく「空き家」に悩む人が年々増加しています。
特に地方では、不動産としての価値がほとんどない空き家も多いです。
「売れない」「貸せない」「住まない」といった“三重苦”の状態に陥ってしまうケースも珍しくありません。
こうした状況のなか、「空き家を国に返す」という発想は、ある種の“最終手段”として関心を集めています。
この社会的背景を踏まえて、2023年4月に正式に施行されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。
これは、相続や遺贈によって取得した不要な土地に限り、一定の要件を満たす場合に国へ引き渡すことを可能にする制度。
従来、日本の法律では所有する土地を手放す手段がほとんど存在せず、「不要だから国に返したい」と思っても法的に不可能な状況が続いていました。
特に所有者不明土地は、公共事業や都市開発を進めるうえでも大きな障害です。
その総面積は、九州全体に匹敵すると言われています。
これにより、国や自治体のインフラ整備や災害復旧が進まない事例も多発していたため、法改正が強く求められていたのです。
制度の概要と利用できるケースの特徴
相続土地国庫帰属制度では、まず土地の所有者が法務大臣に対して申請を行います。
その後、承認を受けたうえで10年分の管理費用を納付することで、その土地の所有権を国に引き渡すことができます。
ここで重要なのは、この制度が対象としているのは、建物のない土地であるという点。
つまり、空き家が建っている状態では制度を利用することができず、あくまで建物を解体して更地にしておく必要があります。
これは、「空き家を国に返す」とは言っても、実際には「空き家を処分し、土地を国に返す」というプロセスを経なければならないことを意味します。
申請する際には、以下の条件をクリアする必要があります。
- 土地が建物付きではない
- 担保権が設定されていない
- 隣接地との境界が明確である
- 土壌汚染や過剰な管理負担がない
また、制度の対象となるのは、相続や遺贈によって取得した土地に限られています。
自分で購入した土地や、すでに長年保有している土地は原則として対象外。
この点を理解せずに申請を行っても、受理される可能性は低いため、注意しなくてはいけません。
制度を活用できれば、長年悩まされてきた「使い道のない土地」から解放されることになります。
しかし、同時に制度のハードルは決して低くありません。
とはいえ、「空き家を国に返す」ための一歩として、こうした法的選択肢が存在するという事実自体が、多くの相続人にとっては大きな救いとなるでしょう。
空き家を国に返すことは可能か?

近年、使われなくなった実家や田舎の住宅をどう処分すれば良いか悩んでいる人が増えています。
その中でよく耳にするのが、「空き家を国に返すことはできないのか?」という疑問です。
結論から言えば、制度上、空き家をそのまま国に返すことはできません。
ただし、一定の手続きを踏み、条件を満たせば、空き家を解体したうえでその土地を国に引き取ってもらうことは可能です。
「相続土地国庫帰属制度」で対象となるのは、相続や遺贈によって取得した土地。
そこに建物(空き家)が存在している場合は、事前に解体して更地にしておくことが必須条件となっています。
つまり、空き家そのものを国が引き取るわけではなく、「空き家を取り壊した後の土地」についてのみ、国庫への帰属が検討されるのです。
この点で、多くの人が空き家を国に返すことを簡単に実行できると誤解している現実があります。
空き家を解体するには、数十万円から場合によっては100万円以上の費用がかかることもあり、簡単に進められる話ではありません。
また、制度を利用するにあたっては、土地そのものがさまざまな要件をクリアする必要があります。
そのため、「空き家を解体すれば必ず国に引き取ってもらえる」というわけでもないのです。
今までは、相続放棄や売却といった限られた選択肢しかなかった中で、法的に国への帰属という道が開かれたことは、空き家問題に悩む多くの人にとって心強い進展といえるでしょう。
ただし、制度の活用には慎重な判断と、事前の情報収集が不可欠です。
相続土地国庫帰属制度の申請条件と手続き

空き家を国に返すための道として注目される「相続土地国庫帰属制度」ですが、その利用には様々な条件と準備が求められます。
誰でも簡単に申請できるものではなく、土地の取得経緯や状態、申請の手続き、費用負担など、多くのハードルが存在します。
ここでは、制度の利用条件と実際の流れについて詳しく見ていきましょう。
制度を利用できるのは「相続・遺贈で得た土地」のみ
この制度は、すべての土地が対象になるわけではありません。
対象となるのは、あくまでも相続や遺贈によって取得した土地に限られます。
つまり、自分で購入した土地や、贈与や売買により取得した土地は、制度の適用外。
これは、制度が「相続によって不要な土地を手放したい人」を支援する目的で作られているためです。
そのため、相続登記が完了していない場合は、まず登記手続きから始めなければなりません。
例えば、父親から田舎の土地を相続したものの、自分では利用する見込みがなく、維持費や固定資産税の負担が重くなっているという場合、この制度の対象となる可能性があります。
一方で、長年自分で所有していた土地や、過去に購入して放置していた土地などは、この制度を使って国に返すことはできません。
また、複数人で土地を共有している場合には、全員の同意が必要。
共有者間で意見が分かれているケースでは申請が進まないこともあります。
このように、制度を使うには「誰の名義で、どのような経緯で取得した土地なのか」を明確にしておくことが前提となるのです。
申請には10項目以上の厳格な条件をクリアする必要あり
制度の対象となるのは、土地の取得経緯だけではありません。
土地そのものの状態についても、非常に細かな条件が設定されています。
具体的には、法務省が定めた次のような基準をすべてクリアしなければ、国は土地の引き取りを認めません。
- 抵当権や地上権などの担保権が設定されていない
- 他人の通行が前提となる土地でない
- 境界が明確で、隣地との争いがない
- 土壌汚染がない(有害物質の基準超過がない)
- 崖地などで、維持に過大な費用や労力がかからない
- 地上・地下に廃棄物や工作物などが残っていない
- 管理や処分に隣接地所有者との争訟を要さない
- 通常の管理が著しく困難とされる特殊な土地ではない
これらのうち、1項目でも該当すれば申請は却下されます。
「空き家を国に返す」ために解体して更地にしたとしても、こうした土地の状態を満たしていなければ、国に引き取ってもらえないのです。
したがって、申請を検討する場合は、自身の所有する土地が要件を満たしているかを事前に精査しなくてはいけません。
土地家屋調査士や司法書士、不動産会社などに依頼し、状態の確認を行ってから進めることが推奨されます。
手続きの流れと費用の目安
制度を利用するには、所定の申請手続きと費用の負担が伴います。
簡単な申請書提出だけで済むわけではなく、一定のプロセスと支出を経て、はじめて国庫帰属が実現します。
一般的な申請の流れは以下の通りです。
- 必要書類の準備(登記簿、境界確認書など)
- 法務局へ承認申請の提出
- 審査手数料の納付(1筆あたり14,000円程度)
- 法務局による現地調査と審査
- 審査通過後、10年分の管理費を一括で納付
- 納付完了後、国に所有権が移転
注意点として、審査を通過した後に支払う10年分の管理費が申請者の大きな負担になります。
これは、土地の場所や広さに応じて金額が変動しますが、数十万円に達することも珍しくありません。
また、土地の状況次第では解体や測量などの付随費用も必要になります。
加えて、法務局による現地調査が行われる場合、調査に協力しなければなりません。
正当な理由なく調査を拒否すれば申請が却下されることもあり、虚偽の申請を行った場合には、罰則(懲役または罰金)が科される可能性もあります。
空き家を国に返すために、この制度を選ぶことは一つの選択肢。
ただし、安易に申し込むのではなく、手続きと費用の全体像を把握した上で、慎重に検討することが大切です。
空き家を国に返す以外の選択肢

「空き家を国に返す」という選択肢は、費用や条件、手続きの煩雑さなどから断念せざるを得ないケースも少なくありません。
そこでここでは、空き家や相続した土地を手放すために考えられる他の現実的な方法について紹介します。
制度以外の選択肢を知ることで、より自分に合った対応策が見えてくるかもしれません。
不動産会社や専門業者への売却
空き家の処分方法として、最も一般的かつ王道といえるのが「売却」です。
不動産会社に依頼して市場に出すことで、買い手が見つかれば比較的スムーズに手放すことができます。
建物の状態や立地によっては、「古家付き土地」として売却できる場合もあるため、まずは査定を受けてみるのが良いでしょう。
「空き家ZERO」では、国に返す予定だった空き家でも、売却をサポートできます。
まずは、私たちに相談してみませんか?
解体して更地として管理・売却する
もし建物の老朽化が著しく、安全性や近隣への影響が懸念される場合は、空き家を解体して更地にするという選択肢も有効。
解体には費用がかかるものの、更地にすることで売却しやすくなったり、特定空家としての行政指導を回避できたりするメリットがあります。
一方で、更地にすると固定資産税が高くなるというデメリットもあります。
そのため、維持するか売るかの判断は慎重に行わなくてはいけません。
ただ、空き家を国に返すのならば、いずれにしても更地にする必要があるため、解体は処分方法を問わず検討対象に上がるでしょう。
また、自治体によっては、老朽化空き家の解体に対する補助金制度を設けている場合もあるので、まずは市区町村の住宅課などに問い合わせてみるのが良いでしょう。
空き家バンクや自治体制度の活用
地方自治体やNPO法人が運営する「空き家バンク」は、空き家を安価で譲渡または売買できる仕組みです。
都市部に比べて買い手は限られるものの、移住希望者や地域活性化を目的とした人々とのマッチングによって、需要が生まれるケースもあります。
自治体によっては、空き家バンクに登録することで、リフォーム補助金や仲介支援制度を利用できる場合もあります。
空き家を「資産」として再利用してもらえる可能性があるため、国に返す以外の選択肢として注目に値します。
一部地域では、空き家を地域交流拠点やシェアスペース、古民家カフェなどに活用してもらう事例も出てきていて、社会的価値としての再評価も進んでいます。
寄附・無償譲渡という方法も
あまり知られていませんが、空き家や土地を個人や団体へ無償で譲渡するという方法もあります。
隣接地の所有者に対して譲渡することで、買い手が見つからない物件でも受け入れ先が見つかるかもしれません。
また、自治体やNPOなど一部団体が、条件付きで土地や建物を受け入れてくれる場合もあります。
ただし、「誰でも無条件に受け取ってくれるわけではない」ため、事前の交渉や書面での契約が必要です。
寄附は所有権が完全に移転するため、「空き家を国に返す」場合と同様に所有者の責任を解除できる点では、確実な手段の一つとなり得ます。
相続放棄という最終手段
空き家の相続自体を拒否する「相続放棄」も、制度的には有効な手段です。
相続放棄をすれば、その空き家をはじめ、被相続人のすべての資産と負債の相続権を失います。
ただし、相続放棄には家庭裁判所への申述手続きが必要。
原則として、相続開始から3ヶ月以内に行わなくてはいけません。
すでに相続登記を済ませてしまった後では放棄が認められにくいため、判断は早期に行う必要があります。
相続放棄をすれば、空き家を管理する義務はなくなります。
一方で、他の財産もすべて放棄しなければならないという大きなデメリットもあるため、慎重な判断が求められます。
空き家を国に返す前に最適な選択肢を知る

空き家の管理や処分に悩む中で、国に返すという選択肢が登場したことは、多くの相続人にとって希望の光かもしれません。
しかし実際には、相続土地国庫帰属制度には高いハードルがあります。
建物の解体、厳格な申請条件、数十万円に及ぶ費用負担など、誰もが簡単に利用できる制度ではありません。
だからこそ、国に返すことだけに頼らず、売却・活用・寄附・解体といった複数の選択肢を視野に入れて検討することが大切。
専門家のサポートを受けることで、想像以上にスムーズな解決策が見つけられるでしょう。
私たち「空き家ZERO」では、こうした空き家問題を抱える方々のために、売却や利活用などのご相談を随時承っております。
不動産としての価値が低いとされている物件でも、再生の可能性や譲渡先が見つかるケースは数多くあります。
空き家を国に返すことに行き詰まりを感じたら、どうか一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者

高等学校を卒業後、東京トヨペットに3年間勤務。その後、「お客様の気持ちに寄り添った工事をしたい」という思いから独立をし、1989年にサワ建工株式会社を設立。空き家事業だけではなく、新築工事やリフォーム、不動産業など、人が安心して暮らせる「住」を専門に約30年間、東京・埼玉・千葉を中心に地域に根付いたサービスを展開している。東京都の空き家問題に本格的に取り組むべく、2021年から「あき家ZERO」事業を開始。空き家を何とかしたい、活用したいと考えている人へサービスを提供している。