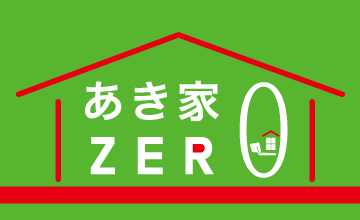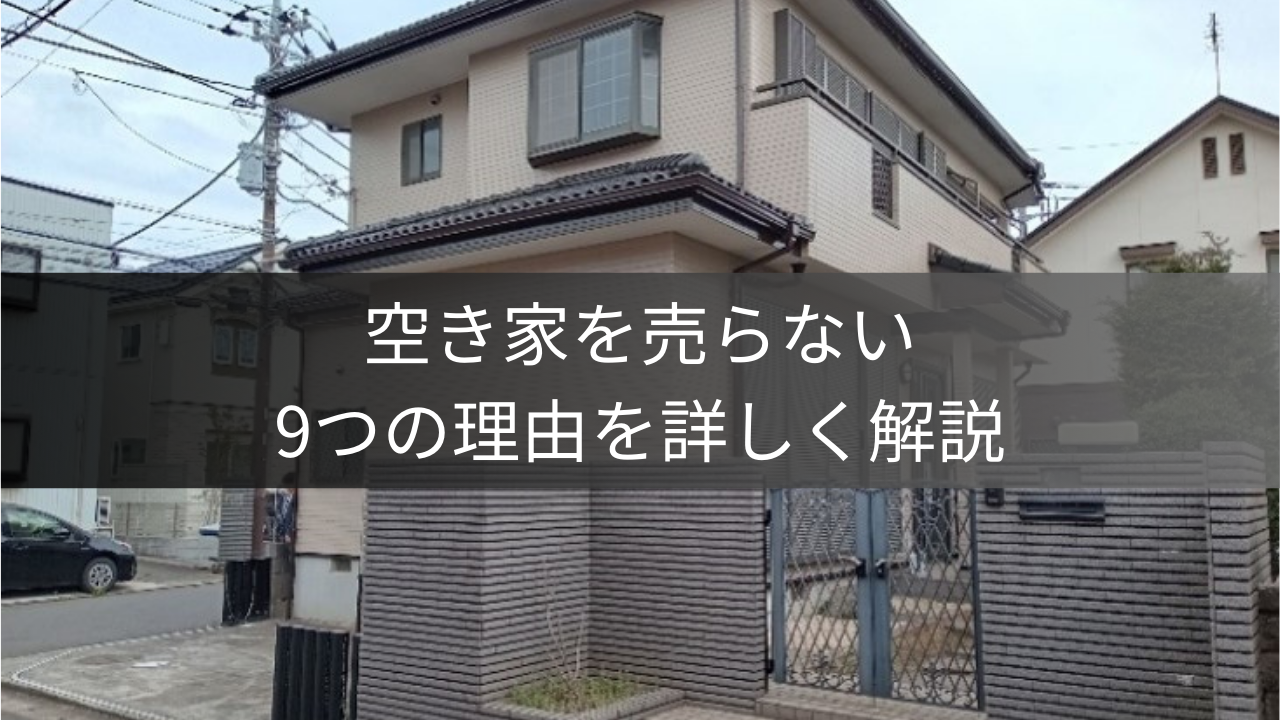放置空き家の割合・放置に潜むリスクと有効活用のための解決策

手入れや管理が放置状態にある空き家は倒壊や景観悪化のリスクが高く、「空き家問題」として問題視されています。
空き家状態にある家は適切に管理を続けるか、解体・売却・貸し出しなどの方法で活用する必要があり、国や自治体をあげて空き家問題の解消に取り組み始めています。
この記事では、放置状態にある空き家の現状と、空き家が問題になる理由や「空き家対策特別措置法」について紹介します。空き家を放置しないための解決策についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
放置されている空き家の現状

総務省統計局では、5年ごとに日本全国の住宅と居住する世帯の状況や土地の実態を把握するために、住宅・土地統計調査を実施しています。
直近の平成30年度住宅・統計調査によると、居住世帯のない住宅のうち、空き家の割合は848万9千戸であり、平成25年の調査から0.1ポイント上昇していることがわかりました。さらに、平成30年の時点で空き家率は総住宅の13.6%と、過去最高の割合になりました。
空き家の内訳と、平成25年比の増減率については以下のとおりです。
【平成30年度の空き家の内訳と増減率】
| 住宅の種類 | 戸数 | 増減率 |
| 賃貸用の住宅 | 432万7千戸 | 0.8%増 |
| 売却用の住宅 | 29万3千戸 | 4.9%減 |
| 二次的住宅(別荘など) | 38万1千戸 | 7.5%減 |
| その他の住宅 | 348万7千戸 | 9.5%増 |
上記の結果では、賃貸用の住宅とその他の住宅が年々増えているとわかります。
「その他の住宅」とは、「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」以外の住宅であり、一例として転勤や入院のため長期にわたって居住者が不在になっている住宅や、建て替えを予定しており取り壊しを待っている住宅が挙げられます。※
※1参照元:総務省「平成30年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要」
空き家の放置は問題になる?

空き家を放置していると、どのようなことが問題になるのでしょうか。4つの問題点について詳しく確認していきましょう。
関連記事:空き家の放置リスクとは?手放したい方におすすめの処分方法5選
理由①老朽化による危険性が高いため
空き家のまま放置していると、メンテナンスや修繕が行き届かず雨漏りやヒビ割れによる老朽化の促進が考えられます。
特に近年では地震や台風、豪雪や豪雨のような災害により建物に被害が発生し、建物自体の倒壊リスクも問題視されています。
地震や地盤の液状化によって強度が失われた建物は、修繕や建て直しを施さなければなりません。それでも放置し続けると、さらなる自然災害によって破損や汚損が進んでしまうのです。
理由②犯罪やいたずらに利用されるリスクがあるため
空き家は雨風をしのぎ、人目に触れないことで犯罪の温床となる可能性もあります。
犯罪者にとっては犯罪行為を行うために身を隠す必要があり、人の目が届きにくい空き家が格好の隠れ場所となってしまうのです。
犯罪者の隠れ場所以外にも、室内への不法侵入やいたずらに利用されるリスクがあり、室内への落書きや火遊びから事故につながるおそれがあります。
理由③地域の景観を損なうため
空き家が比較的新しい状態であれば問題はありませんが、老朽化するほど周辺環境から浮いてしまい景観にも悪影響となります。
例えば、放置状態にあり草木が生い茂って、建物と一体化したような見た目になってしまうと、きれいに整頓され整えられた街並みからは浮いてしまいます。
観光のために整備されているエリアでは、特に空き家の存在が街の景観を乱すおそれがあるため、適切に管理を続けなければなりません。
理由④被災リスクを抱えることになるため
台風や大雨などの災害で被災するリスクが高いことも、空き家を放置してはいけない理由の一つです。たとえば、天候による災害はある程度予測ができるため、本来であれば事前に対策をとることができます。しかし、大雨や長雨で雨漏りしたのにも関わらず、管理を怠り放置していると、カビが映えたり、大きな柱が腐食してしまったり、空き家の状態を悪化させる一方です。また、築年数の古い空き家は、浸水などが起こると漏電の可能性もあり、火災のリスクも高まるでしょう。空き家を放置していると、このような被災リスクもあるため、空き家を管理できる体制を整えることが重要です。
理由⑤近隣住民とトラブルが発生するリスクがあるため
空き家の存在が、近隣とのトラブルを招くケースも少なくありません。
犯罪やいたずらのリスクがあるだけではなく、空き家内部の管理不足により火事が発生し、周辺にも延焼して被害を出したケースがみられます。また、雑草の繁茂によって蚊やハチのような害虫が発生したりするトラブル事例もみられます。
空き家の建材の一部や、庭木が隣家にはみ出してトラブルになる例もあるため、空き家を所有する際には近隣住民への配慮が必要です。
空き家の所有を続けていくリスク
空き家を資産として、あるいは将来的な利用のために所有し続ける場合でも、一定のリスクが発生します。
空き家を保有することで生じる主なリスクは以下の通りです。
税金がかかり続ける
空き家を所有しているだけで、固定資産税や都市計画税などの税金がかかり続けます。
居住や利用の予定がないのに毎年税金を支払うのは大きな負担です。
さらに、管理が行き届かず特定空家等に認定されると、固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用されなくなり、税金の負担がさらに増します。
管理責任の負担
空き家の所有者は、その建物および敷地の管理責任を負います。管理が不十分だと、倒壊や火災などにより近隣住民や通行人に損害を与える可能性があります。
こうした事態を避けるために管理を行う必要がありますが、空き家が居住地から離れている場合、現地に行くだけでも大きな負担となります。
地域環境への影響と損害賠償リスク
空き家は、地域環境にも悪影響を及ぼします。多くの空き家があると、周辺の景観や防犯性が低下し、最終的には地価や住宅価格の低下につながります。
さらに、空き家に関連した事故や事件、火災などが発生し、地域住民に損害を与える場合、所有者は損害賠償責任を負うことになります。
放置した空き家に課される「空き家対策特別措置法」とは

「空き家対策特別措置法(空き家法)」とは、放置状態の空き家に起こりうる問題を解決し、建物の再利用や処分を促すために創設された法律です。
空き家法では、空き家の定義を定めたうえで、各自治体に空き家の確認と調査を行う権限を認めています。そのうえで、2023年12月13日には「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行され、空き家の所有者と国、自治体への責務強化が定められました。
空き家が適切に管理されず倒壊のおそれや景観を損なうリスクが高まると、「管理不全空き家」「特定空き家」に認定されます。
管理不全空き家・特定空き家は一般の住居に適用されている固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用外となるため、税の負担が大きくなってしまう点にも注意が必要です。
ここからは、管理不全空き家から特定空き家に指定されるまでの流れを確認していきましょう。
関連記事:空き家の解体に補助金が使える?その理由と条件について解説
①改善を求められる
空き家の存在が確認されると、自治体ごとにそれぞれの空き家の状態や居住実態の把握に取り掛かります。
具体的には、空き家の所有者に対して建物の除却や修繕、敷地内の立木の伐採や周辺の生活環境の保全に配慮するよう助言や指導を実施します。
居住者や所有者のいない空き家となってから、1年以上〜一定期間が経過すると「管理不全空き家」として認定される場合があります。管理不全空き家は行政による指導や助言の対象となり、指示に従わなければ次の段階である勧告に移ります。
②勧告を受ける
助言を行ったにも関わらず、その空き家の状態が改善されていないと認められたときは、猶予期限を設けたうえで必要な措置をとる旨を勧告します。
勧告は命令の前段階であり、特定空き家の所有者は罰金や固定資産税の特例除外リスクを考慮しなければなりません。
勧告では、「空き家の敷地が固定資産税等の住宅用地の特例から除外される」「周辺の生活環境を保全するために必要な措置を講じる」などの旨が所有者に伝えられます。
ただし、勧告を受けてすぐに特例が外されるわけではなく、改善に要する「相当の期間」を設けたうえで勧告措置となるため、改善措置がとられた場合は住宅用地の特例が適用されます。
③命令を受ける
勧告を受けても改善がみられなければ、次の段階として命令が出されます。命令は行政代執行の前段階であり、命令に従わなければ50万円以下の過料(罰金)を支払わなくてはなりません。
④行政代執行が行われる
命令の履行が適切ではない場合、最終段階として行政代執行が行われます。行政代執行の内容としてはゴミの撤去・庭木の剪定や伐採・建物の解体(除却)などです。
履行が適切ではないケースは以下のとおりです。
【行政代執行の対象となるケース】
- 命令が適切に履行されないとき
- 命令を履行したが十分ではないとき
- 命令を履行したが期限までに完了する見込みがないとき
- 特定空き家の周辺環境への影響が大きく緊急性が高いとき
所有者が命令に応じないケースに加えて、命令の履行が不十分または期限を超過するようなケースでは、周辺環境への影響を考慮して行政代執行が実施されます。
放置した空き家にかかる固定資産税の計算方法

まずは、空き家の固定資産税と都市計画税について以下の表をみてみましょう。
| 小規模住宅用地(200平米まで) | 標準課税額の6分の1 | 標準課税額の3分の1 |
| 一般住宅用地(200平米を超えた部分) | 標準課税額の3分の1 | 標準課税額の3分の2 |
通常、空き家の固定資産税は、住宅用地の特例により、200平米以内の住宅で標準課税額の6分の1に減税されます。しかし、倒壊の恐れや景観や衛生環境を著しく損なうなど、老朽化した空き家を放置し続けると自治体から「特定空き家」に指定されます。その後、自治体からの改善勧告にも応じない場合、この特例措置が適用されず、固定資産税が標準課税額の6倍になってしまうというわけです。
放置した空き家が管理不全空き家に指定されて行政の助言・指導に従わないと、固定資産税や都市計画税に対して適用されている「住宅用地の特例」が除外されます。
住宅用地の特例とは、土地の中に住宅やアパートのような居住用の家屋がある場合、その土地にかかる税を軽減するものです。
通常、固定資産税は土地・建物の固定資産評価額に対して1.4%、都市計画税は土地・建物の固定資産評価額に対して0.3%が課されており、特例を受けると土地にかかる固定資産税が6分の1に、都市計画税が3分の1に抑えられます。
特例が外れると固定資産評価額に1.7%が課税されるため、計算式は以下のとおりです。
【固定資産税評価額が土地1,200万円・家屋800万円の場合の課税額】
| 一般の住宅・空き家
管理不全空き家(勧告前) |
土地:1,200万円×1.4%×1/6+1,200万円×0.3%×1/3=円
(2.8万円+1.2万円=4万円) 建物:800万円×1.4%=11.2 万円 合計:15.2万円 |
| 管理不全空き家(勧告後) | 土地:1,20万円×1.4%+1,200万円×0.3%
(16.8万円+3.6万円=20.4万円) 建物:800万円×1.4%=11.2 万円 合計:31.6万円 |
関連記事:空き家の固定資産税が6倍になる理由と軽減措置を継続する方法
「空き家は解体する」だけが選択肢じゃない
空き家を放置し続けると、さまざまなデメリットがあり、他の人々に迷惑をかける可能性もあります。
この問題を解決するための方法の一つとして、使われなくなった建物を解体することが考えられます。ただし、安易に解体を決断すると思わぬ結果を招くこともあります。
空き家を解体することを検討する際に考慮すべきポイントを紹介します。
解体費用は100万単位
まず、空き家を解体するための費用を捻出できるかどうかが問題となり、一般的な木造住宅の解体には、100万円から200万円程度の費用がかかると言われています。
解体費用の相場は地域や建物の大きさ、構造によって異なりますが、一般的には100万円以上かかると考えられます。
普段の生活の中で突然100万円以上の出費が必要となることは、多くの人にとって大きな負担となるでしょう。
固定資産税の優遇措置もなくなる
建物を解体すると、固定資産税や都市計画税の優遇措置が失われることも考慮すべきです。
通常、不動産には1.4%の固定資産税が課されますが、住宅用地には税負担を軽減するため、「住宅用地の特例」が適用されます。この特例により、住宅用地の固定資産税は最大で1/6、都市計画税は1/3まで減額されます。
一見すると、建物がある方が税金が軽減されるため、解体せずに放置する方が良いと考えるかもしれません。しかし、行政から「特定空家」に認定されると、優遇措置の対象から外れ、固定資産税や都市計画税が上昇します。
特定空家になると、固定資産税や都市計画税が跳ね上がる可能性があります。全ての空き家が対象ではありませんが、所有者にとっては避けたい状況です。
空き家の所有者は、放置を選択肢とせず、解体、売却、活用などの方策を検討する必要があります。
空き家を放置しないための解決策

ここからは、空き家を放置しないためにできる解決策について確認していきましょう。
関連記事:空き家の活用事例を紹介!建物を壊さない利活用とは?
①売却する
空き家を手放す方法としては、知人や家族、その他の第三者に売却する方法が考えられます。不動産会社や空き家バンクに登録し、買い手を探す方法もあります。
②貸し出す
売却以外の選択肢としては、建て替えやリフォーム・リノベーションによって介護施設やシェアハウスにする、空き家バンクを経て旅行者や出張による長期滞在者に貸し出すような方法が挙げられます。
③別の用途で活用する
空き家を取り壊して土地を駐車場に整備したり、畑・倉庫・太陽光発電システムの設置場所にしたりする用途変更も可能です。
それぞれの土地や周辺環境によってニーズが異なるため、利用用途をよく考慮したうえで活用を検討する必要があります。
空き家の将来について検討しよう
今回は、放置されている空き家の現状と放置のリスク、管理不全空き家・特定空き家に指定される流れと、固定資産税などの税金について紹介しました。
空き家をそのまま放置すると、メンテナンスが行き届かないためにさまざまなリスクや周辺環境への影響が考えられます。自治体による調査や指導が入る可能性もあるため、空き家になる建物や土地については早めに対策を考えたいところです。
各自治体では、空き家バンクや空き家に関して相談できる行政の窓口が整備され、空き家問題を防ぐための対策が進められています。ぜひこの機会に土地や建物の活用について検討してみてはいかがでしょうか。
空き家の活用をお考えなら、「あき家ZERO」にお任せください。
この記事の監修者

高等学校を卒業後、東京トヨペットに3年間勤務。その後、「お客様の気持ちに寄り添った工事をしたい」という思いから独立をし、1989年にサワ建工株式会社を設立。空き家事業だけではなく、新築工事やリフォーム、不動産業など、人が安心して暮らせる「住」を専門に約30年間、東京・埼玉・千葉を中心に地域に根付いたサービスを展開している。東京都の空き家問題に本格的に取り組むべく、2021年から「あき家ZERO」事業を開始。空き家を何とかしたい、活用したいと考えている人へサービスを提供している。