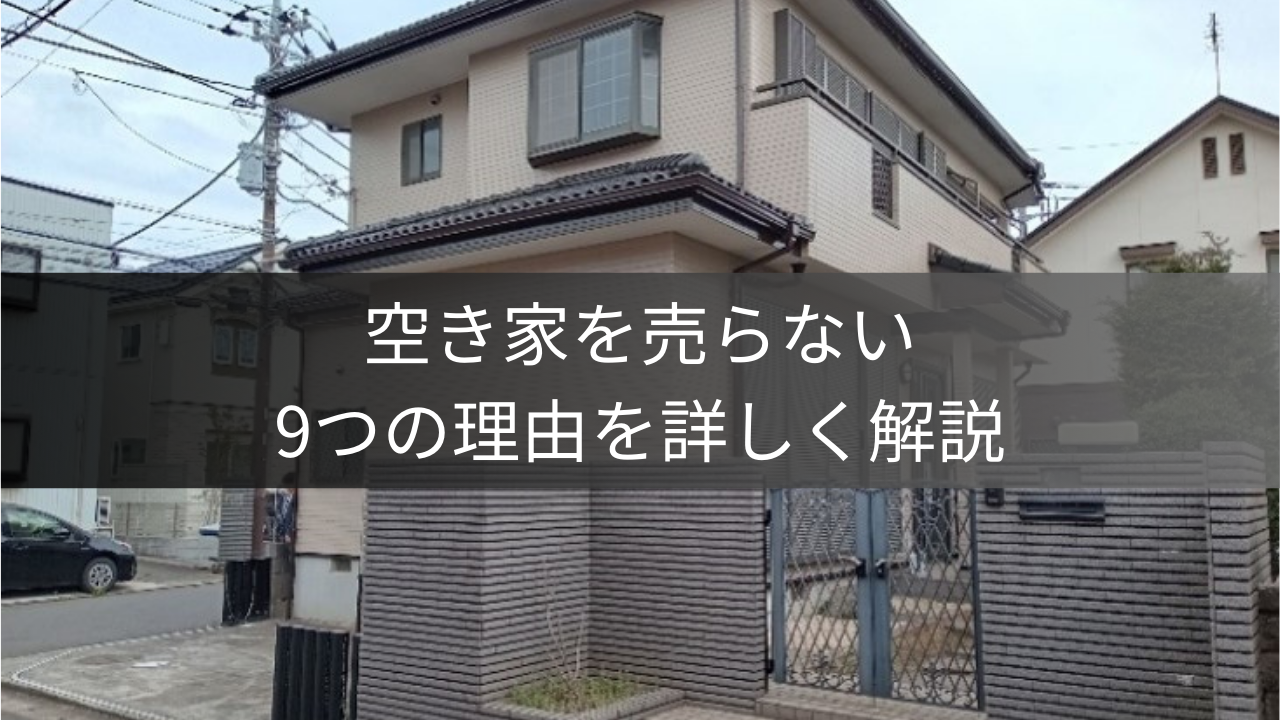空き家ビジネスは儲かる?メリット・デメリットと成功のポイントについて解説

日本全国で増え続けている空き家の多くが、活用方法を見出せず、ただ放置されているのが現状です。
しかし今、そんな空き家をビジネスとして活用する動きが注目を集めています。
賃貸・シェアハウス・民泊・オフィス・駐車場など、空き家の使い道は想像以上に幅広く、上手に活用できれば収益源に変えることも夢ではありません。
もちろん、すべての空き家がビジネスに適しているわけではありませんし、失敗を防ぐには事前の準備と知識が不可欠です。
そこで本記事では、「空き家ビジネスって何?」「本当に儲かるの?」「どう始めればいい?」といった疑問にお答えしながら、メリット・デメリット、活用事例、成功のポイントまで徹底的に解説します。
空き家を持て余している方も、これから相続する可能性がある方も。
今すぐ行動すれば、その空き家は“負担”ではなく“可能性”になるかもしれません。
目次
空き家を活かす!注目の空き家ビジネス5選

空き家ビジネスとは、空き家をそのまま維持・保有するのではなく、収益化・資産化を目的として何らかの形で事業的に活用することを指します。
以下では、比較的取り組みやすく、再現性も高い空き家ビジネスの中から、代表的な5つをご紹介します。
- 賃貸物件
- シェアハウス
- 宿泊施設
- シェアオフィス
- 駐車場
賃貸物件
最もスタンダードで安定性の高い空き家活用方法が、居住用の賃貸物件として貸し出すビジネスです。
これは、空き家を一般の入居者に対して貸し出すことで、月々の家賃収入を得る仕組み。
不動産投資の中でも、比較的低リスクかつ取り組みやすいのが特徴です。
空き家がすでに一定の居住条件を満たしている場合には、最低限の修繕やクリーニングで入居可能になるケースも。
入居者がいることで空気の入れ替えや定期的な清掃も自然と行われ、物件自体の老朽化を抑えられます。
ただし、物件の立地や築年数によっては借り手が見つからないかもしれません。
そのため、事前にエリアの賃貸需要や競合物件の状況を調査することが重要です。
また、空室が続くと収益が発生せず、逆に維持費や税金だけがかかる状態になるため、空室対策として家賃設定やリフォーム内容には工夫が求められます。
シェアハウス
空き家をシェアハウスに転用するのも、有力な空き家ビジネスのひとつです。
これは、1棟の空き家を複数人が共同で暮らせるようにリノベーションし、各居室を個別に貸し出す方法。
1軒の空き家から複数の家賃収入を得ることができるため、通常の賃貸よりも収益性が高くなる可能性があります。
また、シェアハウスは若年層や地方移住希望者に人気があり、SNSなどを通じて入居希望者が集まりやすい傾向にあります。
交流を目的としたコンセプト型シェアハウス(クリエイター向け、外国人向けなど)も増え、空き家の活用と地域活性を両立させるビジネスモデルとして注目されています。
一方で、共同生活によるトラブルや、生活音の問題、防犯面なども大きな課題。
事前に利用規約や入居ルールを明確にするなどの準備が必要です。
初期段階でのリフォーム費用や家具の設置費用などもかかるため、採算ラインを慎重に見極めることが求められます。
宿泊施設
空き家を短期滞在型の宿泊施設として運用する、いわゆる民泊ビジネスも非常に人気の高い空き家活用法です。
Airbnbや楽天トラベルなどのプラットフォームを活用すれば、個人でも簡単に宿泊予約システムを構築でき、比較的低コストで運営を始められます。
このビジネスモデルの魅力は、継続的な家賃収入ではなく、1泊ごとの宿泊料によって高単価を狙える点。
例えば観光地やイベント会場の近くであれば、通常の賃貸よりも高い稼働率と単価を両立できる可能性があります。
リフォームの自由度も高く、築古の空き家を古民家風にアレンジしたゲストハウスなど、デザイン性を重視した運営が可能です。
ただし、集客・レビュー管理・清掃手配など、運営コストが想像以上にかかることも。
オーナーが関わらずに回したい場合は、運営代行業者との連携も検討した方が良いでしょう。
また、地域によっては条例や旅館業法の制限を受けることもあるため、法的な確認を忘れずに行う必要があります。
シェアオフィス
都市部や交通利便性の高い立地にある空き家を持っていますか?
そうであれば、シェアオフィスやコワーキングスペースとしての活用も非常に有効です。
これは、空き家の一部または全体を仕事場として貸し出すビジネス。
法人や個人事業主、フリーランスなどの利用者に向けて、デスクスペースや会議室を時間単位または月単位で貸し出します。
このモデルのメリットは、区画ごとに複数の契約が可能なため、1棟あたりの収益が高くなりやすい点。
物件の構造や広さに応じて自由にレイアウトを設計できるため、他施設との差別化も図りやすくなります。
注意点としては、ビジネス用途に必要なネット環境やセキュリティ設備の整備が求められること。
初期投資にある程度の予算が必要となることが挙げられます。
ただし、補助金の活用や行政との連携でコストを抑えることも可能です。
地域創生やテレワーク推進の動きと結びつけた空き家ビジネスとしては非常に将来性の高いジャンルといえるでしょう。
駐車場
建物としての再利用が困難な空き家の場合、解体して駐車場として活用するという手段も現実的なビジネスモデルとなります。
これは特に老朽化が進み、安全性に不安がある物件に対して有効。
解体後に更地として駐車場運営を行うことで、少額ながら安定した収益を得ることが可能です。
月極駐車場としての活用であれば、固定利用者を確保することで、毎月の収入が見込めます。
時間貸しにすれば、短時間の利用者を取り込むことも可能です。
駅前や商店街の近く、観光地周辺などでは駐車場の需要が高く、空き家をそのまま放置するよりも圧倒的に収益性が高まります。
ただし、舗装工事や照明、防犯設備の整備には初期費用がかかるのは懸念点。
想定される稼働率や賃料設定と照らし合わせながら、回収計画を立てなくてはいけません。
建物を使ったビジネスに比べると収益性は劣りますが、管理負担が非常に少なく、リスクの少ない空き家活用法としておすすめできます。
空き家ビジネスのメリット・デメリット

空き家を使ったビジネスにはさまざまな可能性がありますが、当然のことながらメリットだけではなく、リスクや注意点も存在します。
ここでは、空き家ビジネスの代表的なメリットとデメリットについて、別々の切り口から深掘りして解説していきます。
空き家ビジネスのメリット
「空き家=負担」と考えがちですが、活用方法次第ではその価値は大きく変わります。
空き家ビジネスの最大のメリットは、使われていなかった空き家を“収益を生む資産”に変えられる点。
これにより、これまで維持費や税金といったコストを一方的に支払い続けていた所有者が、逆に安定した収入を得られるようになります。
さらに、空き家を誰かに使ってもらうことで、建物の老朽化を遅らせることができる点も見逃せません。
人が出入りしない家は湿気やカビ、シロアリの被害を受けやすく、あっという間に劣化してしまいます。
ところが、定期的に換気や掃除がされていれば、建物の寿命は確実に伸び、結果として資産価値の維持にもつながるのです。
また、空き家ビジネスを継続することで、特定空き家に認定されるリスクも回避できます。
空き家が実際に活用されている状態であれば、自治体から「管理不全」と判断されることはまずありません。
その結果、固定資産税の減税措置を維持できるというメリットも享受できます。
このように、空き家を活かして継続的な収益を得ながら、建物の維持とリスク回避も同時に実現できる点は、空き家ビジネスならではの強みです。
空き家ビジネスのデメリット
どんなビジネスにもリスクはつきものですが、空き家ビジネスも例外ではありません。
特に注意しておきたいのが「初期投資を回収できないまま終わってしまう可能性がある」という点です。
空き家のビジネス活用には、リフォームや清掃、家具の設置、広告費など、少なくとも数十万円以上のコストがかかる場合があります。
しかし、その地域に空き家の活用需要がなかったり、集客がうまくいかなかったりするかもしれません。
その場合、当然ながら投資した資金を回収できないことになってしまいます。
さらに、トラブルリスクも見逃せません。
シェアハウスや賃貸物件では、入居者同士の揉めごとや近隣住民との騒音問題などが発生する可能性があります。
最悪の場合、入居者による物件の損壊や犯罪が起こるケースもあり、その場合は空き家自体の資産価値が大きく損なわれる可能性もあります。
加えて、物件の立地や築年数によっては、行政や周辺住民からの印象が悪く、思わぬ反発を受けることもあります。
つまり、空き家ビジネスは“誰でも必ず成功するわけではない”という現実を理解した上で、事前調査や収支計画、リスクマネジメントをしっかりと行うことが不可欠なのです。
空き家ビジネスを成功させるポイント

空き家ビジネスにはさまざまな可能性がありますが、何となく始めただけではうまくいきません。
物件の立地や状態、需要の有無など、事前の準備やリサーチを怠れば、せっかくの投資が無駄になるリスクもあります。
ここでは、空き家ビジネスを成功へ導くために知っておきたい3つのポイントを紹介します。
「やってみたい」と思った方こそ、まずは以下を意識して計画を立ててみてください。
- 専門家に相談して客観的な視点を得る
- 空き家の状態・立地に合ったビジネスを選ぶ
- 空き家ビジネスで利用できる補助金を活用する
専門家に相談して客観的な視点を得る
空き家ビジネスに初めて取り組む人にとって、自分だけの判断で進めるのは非常に危険です。
地域の市場環境や物件の状態によって、選ぶべき活用方法や必要な投資額は大きく異なります。
そこで活用したいのが、「空き家ZERO」のような、空き家の活用や不動産運用に詳しい専門家の存在です。
相談に乗ることもでき、活用方法や売却についての手続きなども対応できます。
専門家は、これまでの成功事例や失敗例を多数見てきているため、あなたの空き家にとって最適なビジネスモデルを客観的に提案してくれる存在。
「この家で本当に収益化できるのか?」「シェアハウスと賃貸、どちらが良いのか?」といった疑問がある場合は、迷わず相談してみることをおすすめします。
空き家の状態・立地に合ったビジネスを選ぶ
どんな空き家にも、すべてのビジネスモデルが適しているわけではありません。
老朽化が進みすぎた空き家を賃貸にするには、多額のリフォーム費用がかかってしまいます。
古い住宅地の一軒家をコワーキングスペースにしても、需要がなければ収益は上がりません。
大切なのは、その空き家が持つ特徴をきちんと把握し、実現可能性の高いビジネスを選ぶこと。
例えば、築古でも風情のある空き家であれば、古民家ゲストハウスとして観光需要を狙う戦略が考えられます。
また、大学の近くや繁華街であれば、低価格のシェアハウスとして若者向けに貸し出すのも有効です。
逆に、どうしても活用用途が見つからないような立地であれば、解体して更地にし、駐車場として活用するなど、実利重視の方向転換も視野に入れるべきでしょう。
空き家をビジネスに変えるには、物件に合わせて柔軟な発想で対応していくことが欠かせません。
空き家ビジネスで利用できる補助金を活用する
空き家を活用したビジネスでは、リフォーム費用や設備導入などの初期コストが避けられません。
しかし、こうした費用の一部を補助してくれる制度があることをご存じでしょうか?
実は全国の自治体では、空き家対策の一環として解体費・改修費・設備導入費などに補助金を出す制度を整備しているところが多くあります。
ある市町村では、空き家の解体費用の半額(最大50万円)まで支給されることも。
補助金を活用すれば、費用負担を大幅に軽減しながらビジネスを始めることが可能です。
補助金には申請期間や条件があるため、事前に自治体の公式サイトや窓口で最新の情報を確認しておきましょう。
また、補助金だけに頼るのではなく、将来的な収支を見据えたうえで計画を立てることが、空き家ビジネスを継続させるための土台になります。
| 補助金・助成金 | 補助金額 | リンク |
| 笠間市空き家解体撤去補助金 | 解体費用の1/2かつ補助金額上限50万円 | 公式サイト |
| 老朽空家住宅除却助成事業 | 解体費用の2/3かつ補助金額上限100万円 | 公式サイト |
| 福岡市空き家活用補助金 | 改修工事・設計・解体などにかかる費用の1/2かつ補助金額上限100万円 | 公式サイト |
空き家ZEROがビジネスをサポート
日本全国で空き家が急増している今、単に放置しておくのではなく、価値ある資産として再活用するという考え方が求められています。
空き家を活用できれば、収益が生まれるだけでなく、老朽化リスクや固定資産税の負担、近隣トラブルといった課題も一気に軽減できます。
一方で、空き家ビジネスには初期費用や運営の手間、地域ニーズとのズレなどのリスクも存在します。
こうした不安や疑問がある方は、無理に一人で抱え込まず、信頼できる専門家に相談することが何よりの近道です。
私たち「空き家ZERO」では、空き家の状態や立地、ご希望に合わせて、「売却」「有効活用」「引き取り」の各種サポートを提供しています。
「この空き家、何かに使えないかな?」「今はビジネスにできないけれど、処分したい」
そんなお悩みにも、私たちは親身に対応します。
この記事の監修者

高等学校を卒業後、東京トヨペットに3年間勤務。その後、「お客様の気持ちに寄り添った工事をしたい」という思いから独立をし、1989年にサワ建工株式会社を設立。空き家事業だけではなく、新築工事やリフォーム、不動産業など、人が安心して暮らせる「住」を専門に約30年間、東京・埼玉・千葉を中心に地域に根付いたサービスを展開している。東京都の空き家問題に本格的に取り組むべく、2021年から「あき家ZERO」事業を開始。空き家を何とかしたい、活用したいと考えている人へサービスを提供している。