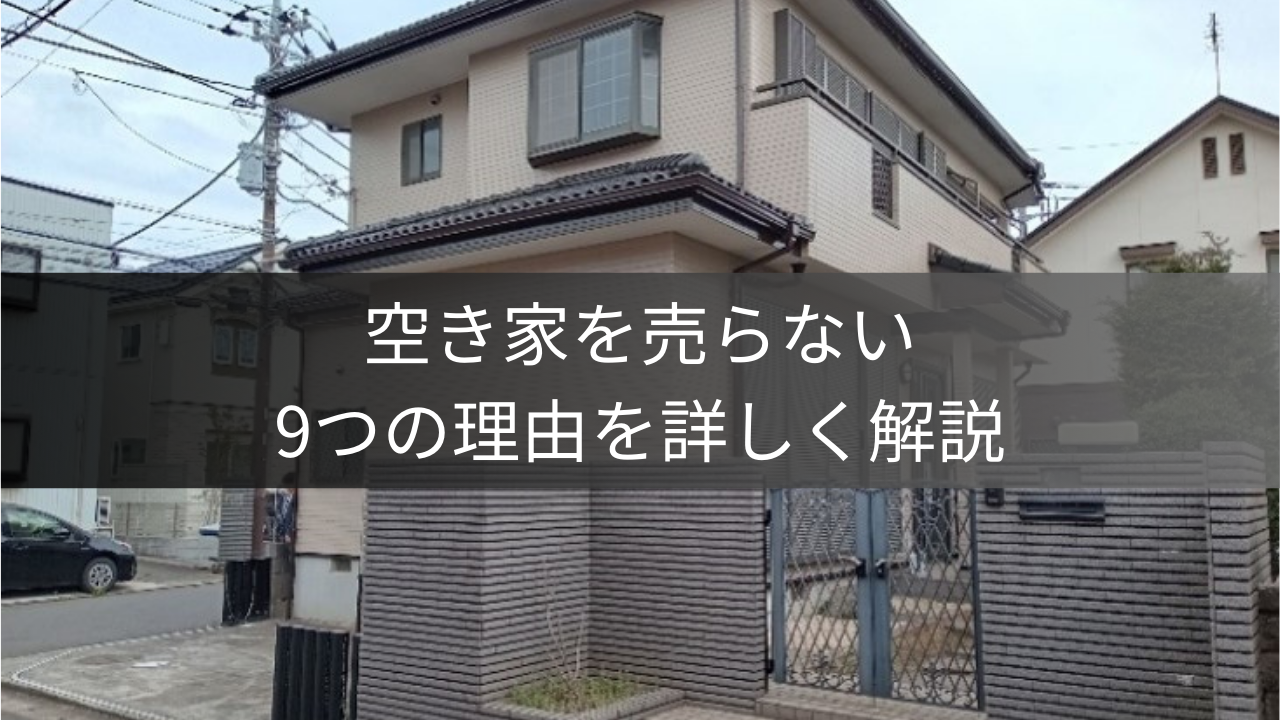田舎の空き家は処分しないとどうなる?放置によるデメリットと手放す方法を解説

「いつか使うかもしれない」という理由で、田舎にある空き家をそのまま放置していませんか?
実は今、日本全国で空き家の処分に悩む人が急増しています。
特に田舎では、不動産需要の少なさや建物の老朽化が重なり、売れない・貸せない・管理できないという三重苦を抱えているケースも少なくありません。
固定資産税の負担、倒壊による損害賠償、特定空き家への認定など、放置された空き家は知らないうちにリスクとコストを生み出す「負の資産」となっていきます。
この記事では、そんな田舎の空き家を処分せずに放置することで起きるリスクと、確実に手放すための具体的な方法をわかりやすく解説します。
「もうどうにもならない」と諦める前に、ぜひ一度この記事をご覧ください。
あなたの空き家に、新たな活路が見つかるかもしれません。
目次
田舎の空き家を処分しないことで発生する2つのリスク

「田舎の実家、放置していても大丈夫」
そう思っていませんか?
確かに、遠方にある空き家の処分は手間がかかり、後回しにされがちです。
しかし、空き家を長期間放置していると、思わぬコストやトラブルに発展するリスクが潜んでいます。
特に田舎の空き家は、管理の手が行き届かないことが多く、都市部に比べて倒壊や特定空き家認定のリスクも高くなりがちです。
ここでは、田舎の空き家を処分しないことで生じる2つの代表的なリスクをご紹介します。
- 老朽化が進み倒壊する
- 特定空き家に認定される
老朽化が進み倒壊する
空き家は、人が住んでいないだけで一気に劣化が進みます。
特に田舎では、湿気の多い土地や強い日差し、冬の積雪など、自然環境によって建物の傷みが加速します。
放置された空き家は、換気不足による湿気・カビ・木材の腐食が起きやすく、やがてシロアリなどの被害にも繋がるかもしれません。
構造材が弱まれば、台風や地震など自然災害の際に倒壊のリスクが急激に高まります。
そして問題は、倒壊によって第三者に損害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を負うこと。
実際に、通行人の死亡事故や隣家の破損などが発生し、数千万円単位の賠償請求を受ける事例もあります。
「いつか使うかも」と放置された家が、知らぬ間にリスクを生み、大きな損失を生む原因になる可能性もあるのです。
特定空き家に認定される
空き家の管理状態が悪化すると、自治体から「特定空き家」に認定される可能性があります。
これは、空き家等対策特別措置法に基づき、危険性や周囲への悪影響が大きいと判断された建物に対して適用される制度です。
具体的には以下のような状態が該当します。
- 倒壊や崩落の危険がある
- 害虫・異臭などで衛生面に問題がある
- 景観や周辺の生活環境を著しく損ねている
この認定を受けると、固定資産税の優遇措置が失われ、税負担が大幅に増加します。
さらに、自治体から改善命令や解体命令が下され、それを無視した場合は行政代執行による強制解体と、その費用の請求まで発展します。
つまり「放置しているだけ」のつもりが、法的リスクにまで発展する恐れがあるということ。
日頃の管理や早めの対策が、行政介入を防ぐ大切なポイントとなります。
田舎の空き家を処分するための4つの方法

「田舎の空き家をどうやって処分すればいいのかわからない」
そんな声は少なくありません。
都市部と異なり、田舎では不動産の需要が低く、処分のハードルが高いという現実があります。
しかし、リスクを抱えたまま放置しておくことの方が、長期的には大きな負担になります。
ここでは、田舎の空き家を手放すための現実的な4つの方法をご紹介します。
物件の状態や立地条件に応じて、最適な処分方法を検討してみてください。
- リフォームして売却する
- 売却が難しい場合は寄付という選択肢も
- 物件の状態が良ければ賃貸物件にすることも可能
- 相続放棄という方法も選択肢のひとつ
リフォームして売却する
田舎の空き家であっても、適切にリフォームを行えば売却できる可能性は十分にあります。
古民家ブームや地方移住のニーズから、あえて田舎の中古物件を探している人も一定数存在します。
ただし、老朽化が進んでいる空き家は、外観や内装の劣化が目立つため、買い手の不安要素になりやすいのが現実です。
そのため、「まずは見た目を整える」ことが売却成功のカギになります。
必要最低限のリフォームや修繕を行うことで、物件の印象が大きく変わり、売却価格の上昇やスムーズな契約成立につながる可能性が高まります。
また、田舎の空き家を売却する際は、自治体の「空き家バンク」を活用するのも有効な手段です。
不動産会社の仲介手数料を抑えつつ、購入希望者とのマッチングができるため、費用対効果の高い選択肢となります。
売却が難しい場合は寄付という選択肢も
「ボロボロの空き家」「山奥の立地」「買い手がまったく見つからない」
そんな場合は、思い切って寄付を検討するのも一つの方法です。
空き家の寄付は、自治体・法人・個人などに無償で所有権を譲る形になります。
経済的なリターンはないものの、所有し続けることで発生する固定資産税や管理コストから解放されるという点で、大きなメリットがあります。
ただし注意点として、寄付は「相手が受け入れてくれて初めて成立する」方法です。
老朽化が進んでいる建物や、立地条件が悪い空き家の場合、寄付を断られるケースも少なくありません。
また、寄付先によっては、解体して更地にしてからでないと受け取ってもらえない場合もあります。
このように、寄付は簡単な方法ではありませんが、「どうしても売れない」「自分では管理できない」といった場合には、検討に値する処分手段です。
物件の状態が良ければ賃貸物件にすることも可能
「売るのは難しいけれど、まだ十分住める状態の空き家をどうしよう?」
そんなときには、賃貸物件としての活用を検討するのも一つの選択肢です。
近年では、テレワークの普及やライフスタイルの多様化により、田舎暮らしを求める人も増加。
特に首都圏では、「まずはお試しで地方に住んでみたい」というニーズも高まり、空き家を賃貸として提供することで、地方移住希望者とのマッチングが成立するケースも増えています。
賃貸として貸し出す場合、リフォームや清掃など、初期投資が必要になることも。
しかし、家賃収入によって固定資産税や維持費を補えるメリットがあります。
さらに、定期的に人が住むことで換気や清掃が自然に行われ、老朽化や倒壊リスクも軽減されます。
ただし、田舎ではエリアによって賃貸需要に大きな差があるため、事前の市場調査は必須。
賃貸サイトへの掲載や自治体の相談窓口を利用して、どのような層にニーズがあるのかを確認することが成功のカギとなります。
空き家を売るか処分するかで悩んでいる方は、「活用」という視点から、収益化しながら維持していく方法も検討してみてはいかがでしょうか。
相続放棄という方法も選択肢のひとつ
空き家を引き継ぐタイミングで「自分では使う予定がない」「負担しかない」と感じる場合、相続放棄という方法も選択肢のひとつです。
特に田舎の空き家は、売却が難しく、維持管理にコストがかかることから、相続人にとって「いらない不動産」になりがちです。
相続放棄をすれば、物件の所有権は移らず、固定資産税や修繕費といった経済的負担から完全に解放されます。
将来的に発生するかもしれない倒壊事故や特定空き家の認定リスクも回避できるため、合理的な選択といえるでしょう。
ただし注意点もあります。
相続放棄をすると、空き家だけでなく預貯金や有価証券など、プラスの財産もすべて放棄することになります。
空き家の負担よりも他の資産の方が大きい場合は、総合的に判断する必要があります。
また、相続放棄には期限があり、相続の開始(通常は被相続人の死亡)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
迷っているうちに期限を過ぎると、自動的に相続したことになってしまうため、早めの判断が求められます。
田舎の空き家をどう処分するか迷ったとき、「相続しない」という決断も、将来の安心につながる重要な手段のひとつです。
田舎の空き家を確実に処分するための2つのポイント

ここでは、“確実に手放すための2つの実践的な選択肢”をご紹介します。
田舎の空き家は市場ニーズが限られていることも多く、思ったように買い手や借り手が見つからないことも珍しくありません。
しかし、処分できないからといって放置してしまえば、これまでご紹介してきたように税金・老朽化・行政リスクなど、さまざまなデメリットが発生します。
最終手段としてでも知っておきたい、現実的な対応策を見ていきましょう。
- 建物を解体して土地として売却する
- 相続放棄で空き家の所有を回避する
建物を解体して土地として売却する
「家があるから売れないのでは?」と感じたことはありませんか?
その通り、実は老朽化した建物があることで買い手のハードルが上がってしまうことがあります。
なぜなら、購入者側は建物の解体費や廃材の処分費を自己負担しなければならず、それがネックになるからです。
そのため、あえて空き家を解体し、土地として売却することで買い手の負担を減らすという選択肢があります。
土地であれば、住宅用地だけでなく、資材置き場・畑・駐車場・キャンプ場など、活用用途の幅が広がるため、売却できる可能性が高まります。
もちろん、解体には数十万〜百万円程度の費用がかかりますが、売却がスムーズに進むことでそのコストを回収できる場合もあります。
また、空き家のまま所有し続ける固定資産税・維持費・管理手間を考えると、トータルで見てプラスになることも多いです。
「家を残して売る」ことに固執せず、「土地だけで売る」という柔軟な発想が、田舎の空き家処分成功のカギになるかもしれません。
相続放棄で空き家の所有を回避する
どうしても使い道がなく、管理も難しい田舎の空き家。
相続が発生したタイミングで、「これ以上背負いたくない」と感じたなら、相続放棄という方法も選択肢に入れるべきです。
相続放棄をすることで、対象となる空き家だけでなく、関連する土地・建物の所有権そのものを放棄でき、法的に責任を負わずに済むようになります。
放棄すれば固定資産税の支払い義務や管理義務もなくなり、空き家の倒壊リスクや近隣トラブルに悩まされる心配もなくなります。
ただし、すでに触れたように、相続放棄は他の財産(預貯金や株など)もすべて放棄する行為となるため、総合的な資産価値を見たうえでの判断が必要。
また、相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければならないため、迷っている時間はあまりありません。
「使わない空き家を相続して負担を増やすくらいなら、いっそ手放す」
その決断が、将来のトラブルや金銭的な損失を未然に防ぐ一手となるでしょう。
田舎の空き家処分は今すぐ行動を

田舎の空き家は、都市部に比べて処分が難しい傾向があります。
しかし、放置してしまえば固定資産税や倒壊リスク、特定空き家への認定など、さまざまなデメリットが年々積み重なっていくのが現実です。
「そのうち売れるかも」「まだ使うかもしれない」
そう思っているうちに、空き家の価値はどんどん下がり、やがて誰にも引き取ってもらえない“負動産”になる可能性もあります。
空き家を手放す方法には、売却・賃貸・寄付・相続放棄などさまざまな選択肢がありますが、
「自分でどうにもできない」「買い手がつかない」といったケースでは、「空き家ZERO」が空き家を引き取るお手伝いも可能です。
「手遅れになる前に動く」ことが、空き家問題の最善の解決策です。
この記事の監修者

高等学校を卒業後、東京トヨペットに3年間勤務。その後、「お客様の気持ちに寄り添った工事をしたい」という思いから独立をし、1989年にサワ建工株式会社を設立。空き家事業だけではなく、新築工事やリフォーム、不動産業など、人が安心して暮らせる「住」を専門に約30年間、東京・埼玉・千葉を中心に地域に根付いたサービスを展開している。東京都の空き家問題に本格的に取り組むべく、2021年から「あき家ZERO」事業を開始。空き家を何とかしたい、活用したいと考えている人へサービスを提供している。