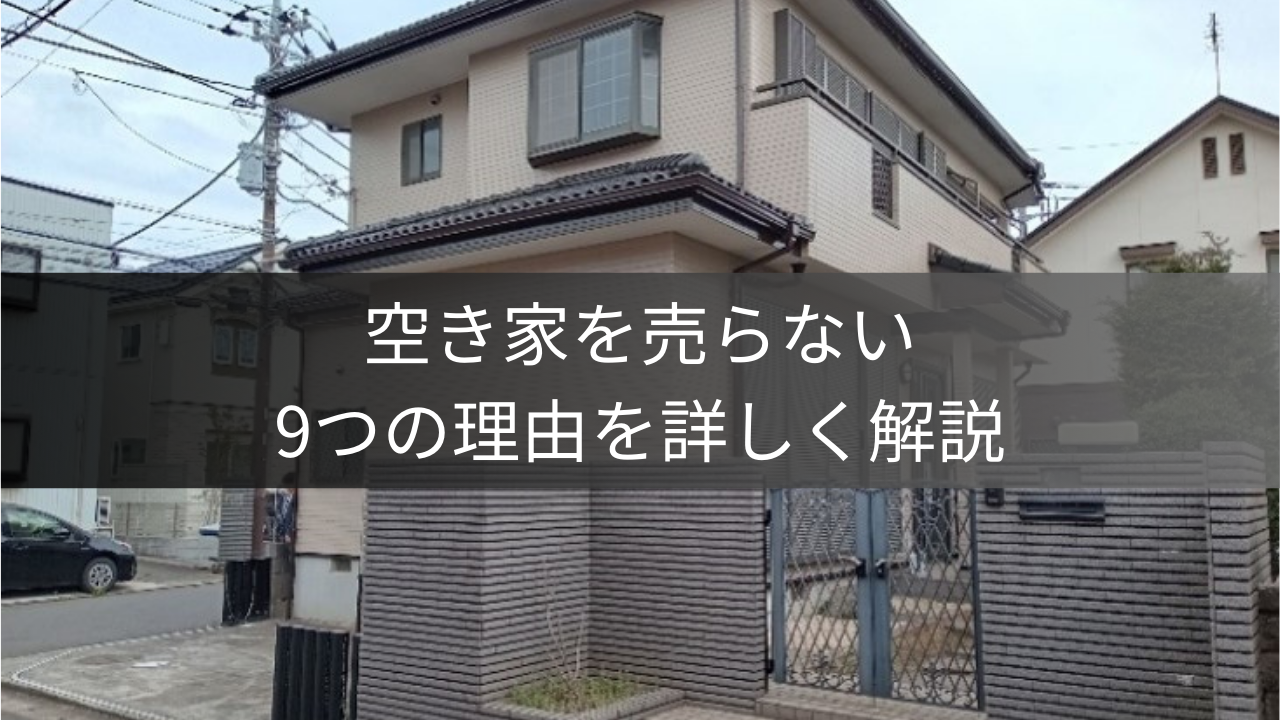栃木で増え続ける空き家──放置せずに“活用”へ踏み出すために

親から相続した実家、転居で残してきた一軒家。
「使い道が見つからないまま、栃木に空き家を抱えている」という人は少なくありません。
思い出が詰まった家だからこそ、売却には踏み切れない。
けれど、管理に通うのは負担で、草刈りや修繕費も積み重なっていく…。
そうした状況のまま何年も放置される空き家が、県内各地で目立つようになっています。
実は今、「売らずに残す」方法も数多く存在します。
リフォームして賃貸に出す、地域活動の場として再生する、補助金を利用して改修や解体の費用を軽くする。
栃木ではこうした“活用”の選択肢が広がりつつあるのです。
この記事では、栃木県で実際に進められている空き家対策や、自治体の補助金制度を交えながら、費用を抑えて活用を始めるための道筋を紹介します。
「まだ決められない」と迷っている方でも、一歩踏み出すヒントが見つかるはずです。
目次
何年もそのままの空き家──「どうすればいいか分からない」あなたへ
「そろそろ片付けなくては」と思いつつ、何もできないまま時間が過ぎる。
そんな空き家を抱える人が栃木でも増えています。
なぜ空き家をそのままにしてしまうのか?
決断を遅らせてしまう理由は、人それぞれです。
家族の思い出が強く残っているため「手放すことは裏切りのように感じる」人もいれば、固定資産税や修繕費をどう工面するか分からず「動き出すのが怖い」と思う人もいます。
さらに、遠方に住んでいて管理に通えない、親族と意見がまとまらないなど、人間関係や距離の問題も大きな壁になります。
このように、感情と現実の負担が重なれば、空き家を放置してしまうのは当然とも言えます。
「なぜできないのか」を知るだけで、自分を責めずに済む。
それが、栃木の空き家を活用する最初のきっかけになるのです。
栃木県でも増えている“動けない所有者”たち
総務省の統計によると、日本の空き家率はすでに13.8%。
栃木県でも「手放せない」「使えない」という空き家が増加傾向にあります。
特に、敷地の広い一戸建てや庭付き住宅の多い地域では、草木の管理や建物の劣化が想像以上に早く進むため、所有者が手を焼いているケースが目立ちます。
県外に住む相続人にとっては「行くたびに1日がかりで作業になる」ことも珍しくありません。
「自分だけが困っているのではない」という気づきは大きな安心材料になります。
同じように迷っている人が栃木に数多くいることを知るだけで、次の一歩を考える余裕が生まれるのです。
https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/g_kekka.pdf
「うちでも活用できるの?」と迷っている方へ伝えたいこと
栃木で空き家を所有していると、「自分の家なんて古いから使えないのでは?」と感じてしまう人は少なくありません。
けれど、実際に空き家活用が進んだ事例を見ると、立地や築年数といった条件よりも大切なのは「どんな視点で家を見直すか」です。
空き家活用がうまくいく人の共通点とは?
「活用できる家」と「できない家」を分ける明確な線はありません。
むしろ、うまくいった人に共通しているのは “できる範囲から動いてみる柔軟さ” です。
例えば、栃木県内では古民家をリフォームして地域の子ども食堂やコミュニティスペースに変えた例もあります。
また、古い一戸建てをリノベーションし、移住希望者や若い夫婦の賃貸住宅として活用するケースも増えています。
こうした人たちは、最初から大きな計画を立てたわけではありません。
「思い出を残したい」「家を無駄にしたくない」といった気持ちを出発点に、地元の団体や専門サービスと連携しながら少しずつ形にしています。
つまり、栃木の空き家を活用する上で必要なのは、条件よりも“姿勢”。
「やってみよう」という気持ちが、結果的に成功につながるのです。
何から始める?最初の順番で8割が決まる
空き家活用を考えるとき、最初の順番を意識するだけで進み方が大きく変わります。
最初に取り組みたいのは「感情の整理」です。
なぜ手放したくないのか、どんな形で残したいのかを改めて確認すると、活用の方向性が自然と見えてきます。
次に大切なのは「現状の把握」です。
建物の築年数や固定資産税額、庭や外壁の劣化具合をチェックし、可能であれば写真を残しておくと、専門家へ相談する際にも役立ちます。
そのうえで「情報収集」を行いましょう。
たとえば、栃木県や市町村が実施している補助金制度を調べると、費用負担を軽くする選択肢が見つかります。
宇都宮市の「老朽危険空き家除却費補助金」などはその一例です【引用元:宇都宮市公式サイト】。
情報が集まったら「相談」に進みます。
行政の窓口や不動産会社、空き家活用サービスなど、自分が話しやすい相手で問題ありません。
相談は契約を意味するものではなく、むしろ状況を整理するための場と考えると気が楽になるでしょう。
最後に「判断」です。
感情と条件、費用面が整理されれば、自分に合う方法が自然に見えてきます。
こうした流れを踏むことで、「何から手をつければいいのか分からない」という不安が薄れ、空き家を活用する行動へとつながっていきます。
「売る」以外にもある、あなたに合った空き家の活かし方
栃木に空き家を持つと、「結局は売るしかないのでは」と考えてしまう人も多いでしょう。
しかし、実際には売却以外にも選べる活用方法が存在します。
ここでは、地域で活かす方法、賃貸として収益化する方法、そして売却によって得られる安心感という三つの視点から紹介します。
誰かの役に立つ空き家──地域で活かすという選択
「家は残したいけれど、自分では住めない」。
そんなときに選ばれているのが、地域での活用です。
古民家を集会所や子ども食堂に活かしたり、趣味の教室やアート展示の場にしたりと、地域の人が集まる拠点に変える事例が栃木県内でも増えています。
たとえば塩谷町では、「空き家改修事業補助金」によって、空き家バンクに登録された物件を修繕する際、費用の二分の一(上限五十万円)が補助されます。
さらに子育て世帯が入居する場合には十万円が加算される仕組みもあります【引用元:塩谷町公式サイト】。
制度を利用すれば、個人の負担を抑えつつ「地域のために活用する」という選択が現実的になります。
空き家は放置すればリスクになりますが、人が使うだけで資産としての価値を取り戻します。
負担ゼロで収益化?賃貸活用という現実的な方法
「管理に通うのも大変だし、リフォーム代を出す余裕もない」。
そんな方にこそ知ってほしいのが、自己負担ゼロで始められる賃貸活用の仕組みです。
栃木市では「空き家改修費補助金」があり、空き家バンク登録物件の改修にかかる経費の一部を最大五十万円まで補助しています【引用元:栃木市公式サイト】。
補助金と専門サービスを組み合わせれば、オーナーが費用を出さずに空き家を再生し、賃貸として貸し出すことも可能です。
また下野市の「空き家バンクリフォーム補助金」では、工事費の二分の一(上限五十万円)が支給されます。
さらに不要な家財道具の処分にも補助が出るため、「片付けが大変で手をつけられない」という人でも活用を進めやすくなっています【引用元:下野市公式サイト】。
オーナーの負担は最小限に抑えられ、入居希望者にとっては魅力ある住宅が増える。
双方にとってメリットのある方法として、栃木でも注目されています。
売却で得られるのは、お金だけじゃない安心感
どうしても維持できない場合や、早めに区切りをつけたい場合には、売却も一つの選択肢です。
「売る=失敗」と考える方もいますが、実際には生活の不安を減らし、心の整理にもつながります。
宇都宮市の「老朽危険空き家除却費補助金」では、倒壊の恐れがある危険な空き家を解体する際、工事費の三分の二(上限七十万円)が補助されます【引用元:宇都宮市公式サイト】。
補助を利用すれば、売却前に解体して更地にすることで買い手が見つかりやすくなるケースもあります。
実際に売却を選んだ人の多くは、「もっと早く決断すればよかった」と話します。
管理の負担から解放され、さらに「新しい所有者が丁寧に使ってくれて安心した」と感じる人も少なくありません。
売却は資金を得る手段であると同時に、心の重荷を軽くする方法でもあります。
自分に合った活用方法の一つとして、前向きに検討してみても良いでしょう。
費用も手間もかけたくない人が知っておきたいこと
「空き家を活用したいけれど、お金や労力はかけられない」。
そう思っている人も多いのではないでしょうか。
実際、リフォーム費用や日々の管理の手間が理由で、行動をためらう方は少なくありません。
ですが今は、工夫次第で自己負担を最小限にしながら、空き家を活かす方法が整ってきています。
ここでは、栃木で空き家を持つ方が「現実的にやれる範囲」で選べる方法を紹介します。
リフォーム代ってどのくらい?自己負担ゼロの仕組みとは?
空き家をリフォームするとなると、「数百万円はかかるのでは」と不安に思う人も多いはずです。
実際、一般的な改修には三百万円以上かかるケースも珍しくありません。
ところが、自治体や専門サービスを利用すれば、自己負担ゼロでリフォームできる仕組みもあります。
たとえば栃木市や下野市では、空き家バンクに登録した物件の改修に対して補助金が用意されています。
費用の二分の一、上限五十万円まで支給される制度があり、活用すれば出費を抑えて再生が可能です【引用元:栃木市公式サイト/下野市公式サイト】。
さらに、あき家ZEROのような専門サービスでは、リフォーム費用を事業者側が負担し、賃貸運用によって回収するモデルも広がっています。
オーナーは初期費用を出さずに済み、改修後の家賃収入の一部を得られる仕組みです。
「お金がかかるから無理」と思っていた人でも、制度や仕組みを知ることで一歩を踏み出せる可能性があります。
相談前に知っておきたい“やること5つ”
専門家に相談する前に、軽く準備しておくと話がスムーズになります。
ここでは、難しくない五つのステップを紹介します。
まず「気持ちの整理」です。
なぜ残したいのか、どんな形で使いたいのかを簡単に言葉にしてみましょう。
次に「現状確認」。
築年数や劣化の程度、固定資産税額などをチェックし、写真を残しておくと役立ちます。
三つ目は「活用の方向性を考える」ことです。
地域に役立てたいのか、収益を得たいのか、まだ決められないのか──ぼんやりでも構いません。
四つ目は「家族との話し合い」です。
相続人や共有者がいる場合は、意向を確認しておくと後のトラブルを防げます。
最後に「相談先の候補を調べる」こと。
行政、不動産会社、空き家専門サービスなど、いくつか候補をリストにしておくと安心です。
この五つを準備しておくだけで、「何を話せばいいのか分からない」という不安が減り、最初の相談がぐっとラクになります。
知らないと損?相続・税金・制度の基本だけ押さえる
空き家を活用するうえで、相続や税金の制度は避けて通れません。
ですが、「むずかしそう」と感じて後回しにする人も多いのが実情です。
2024年からは「相続登記の義務化」が始まりました。
相続した不動産は必ず登記する必要があり、正当な理由なく放置すると最大十万円の過料が科される可能性があります【引用元:総務省】。
また、老朽化が進んで「特定空き家」に指定されると、土地の固定資産税が最大六倍になることもあります。
草木が放置されたり、倒壊の危険がある状態が続けば、優遇措置が解除されてしまうのです。
一方で、解体やリフォームに補助を出す制度も整っています。
宇都宮市や矢板市では、危険な空き家の解体費用に対して上限七十万円や六十万円の補助が用意されています【引用元:宇都宮市公式サイト/矢板市公式サイト】。
こうした制度は、知っているかどうかで数十万円単位の差が出ることもあります。
すべてを自分で調べなくても大丈夫です。
「自分の空き家に関係する制度があるかも」という視点を持ち、早めに相談しておくことが損を防ぐ一歩になります。
「そのうちやろう」が一番損になる理由
「来年でいいか」「時間があるときに考えよう」。
そう思って空き家を先延ばしにしている方は少なくありません。
しかし実際には、放置するほど状態は悪化し、費用やリスクが大きくなってしまいます。
ここでは、放置によって起こりやすい現実的なデメリットを紹介します。
たった数年で修繕費が2倍に?放置の現実
空き家は、人が住まなくなると急速に劣化が進みます。
風通しが悪くなることで湿気がこもり、カビやシロアリが発生しやすくなります。
雨漏りに気づかず放置した結果、柱や梁まで腐食が広がり、修繕費が当初の二倍以上に膨らんだケースもあります。
外壁のひび割れや水道管の破損なども、対応が遅れるほど大掛かりな工事が必要になります。
さらに、劣化が進んだ空き家は売却もしにくくなります。
買い手が見つかったとしても、「解体前提」で安く買い叩かれてしまうことも少なくありません。
だからこそ、「どうせやるなら早めに」が鉄則です。
傷みがひどくなる前に動くことが、最終的なコスト削減につながります。
近隣トラブル・行政指導…誰にも相談できなくなる前に
空き家を放置したままにしておくと、周囲に迷惑をかけるリスクも高まります。
雑草が伸び放題になったり、ゴミの不法投棄や不審者の侵入を招いたりするのは、典型的なトラブルです。
「子どもが近づけない」「景観が悪い」などの苦情が寄せられ、近隣との関係が悪化することもあります。
さらに深刻なのは、行政から「特定空き家」に指定されることです。
指定されると指導や勧告の対象となり、最悪の場合は強制的に解体されるケースもあります。
その際の解体費用は原則として所有者の負担となり、数百万円単位の出費につながります。
矢板市や宇都宮市では、老朽危険空き家の解体に対して補助金制度を設けていますが【引用元:矢板市公式サイト/宇都宮市公式サイト】、申請には期限や条件があります。
気づいたときにすぐ相談しておかないと、制度を利用できずに全額自己負担となる可能性もあるのです。
「そのうち」と思っていたせいで、家族や友人にも相談しづらくなり、孤立してしまう人も少なくありません。
早めに一歩を踏み出すことこそが、自分を守り、周囲に迷惑をかけないための最善策です。
「相談したら断れなくなるんじゃ…」と思っている方へ
「まだ決めていないのに相談していいのだろうか」。
「営業されて、断れなくなったらどうしよう」。
そう感じて、一歩を踏み出せない人も多いのではないでしょうか。
ですが、空き家活用における相談は契約を前提とするものではありません。
むしろ「情報を整理するための時間」と考える方が自然です。
ここでは、相談に進む前に知っておくと安心できる二つの視点を紹介します。
まだ決めてなくても、相談していい理由
「売るか貸すか迷っている」「本当に活用できるのか知りたい」。
こうした漠然とした状態で相談することに、まったく問題はありません。
むしろ、何も決まっていない段階だからこそ、相談の価値があります。
専門家と話すことで、頭の中が整理され、可能性や課題が具体的に見えてきます。
最近では「選択を急がせない相談」を重視するサービスも増えています。
あき家ZEROもそのひとつで、相談した結果「今回はやめておこう」と結論を出す人も歓迎しています。
相談は契約ではありません。
安心して「情報を集める場」として活用してみてください。
家族や友人では解決しない問題があるという話
空き家のことを誰かに相談する場合、最初に思い浮かぶのは家族や友人かもしれません。
しかし実際には、「どうすればいいか分からない」「判断は任せる」といったやりとりで終わってしまうケースが多いのです。
それもそのはず。
空き家の活用には感情や制度、費用など、複雑な要素が絡んでいます。
たとえば、相続登記の義務化や固定資産税の優遇措置の有無、補助金の対象条件などは、専門知識がないと理解が難しい領域です【引用元:総務省/宇都宮市公式サイト】。
また、「売ると家族に責められそう」「兄弟で意見が合わない」といった心理的な葛藤も、身近な人には相談しづらくなる原因です。
だからこそ、第三者であるプロに話す意味があります。
専門家は感情に配慮しつつ、制度や費用面を冷静に整理してくれます。
「売らせよう」とする営業ではなく、あくまで「判断材料を提供する存在」として寄り添ってくれるのです。
家族でも友人でもないからこそできる相談。
それが、空き家問題を前に進める大切なきっかけになります。
あき家ZEROなら、あなたの「迷いごと」に応えられます
「お金はかけたくない」。
「でも手放すのも違う気がする」。
「誰かに任せたいけど、どこに相談すればいいか分からない」。
栃木で空き家を所有する方の多くが、そんな迷いを抱えています。
あき家ZEROは、その「迷い」を整理するための伴走者です。
私たちは売却や賃貸、地域での活用といった方法を押しつけるのではなく、オーナー一人ひとりの気持ちや状況に合った選択肢を一緒に考えます。
たとえば、「初期費用をかけずに賃貸に出したい」という方には、リフォーム費用を自己負担ゼロで始められる仕組みをご提案できます。
「思い出を残したいけれど管理できない」という方には、地域と連携した活用や一部貸し出しといった柔軟な方法を考えます。
遠方に住んでいる方でも安心です。
現地に通う必要はなく、管理から運用までをすべてプロが担います。
「相談しただけで契約を迫られるのでは」と心配される方もいますが、あき家ZEROでは情報整理の場としての相談も歓迎しています。
栃木にある空き家を「負担」ではなく「資産」に変えていくために。
私たちは、オーナーの不安や迷いに寄り添いながら、最適な活用方法を一緒に探していきます。
“決めなくてもいい”からこそ、動いて損はない時代
栃木で空き家を所有していても、「どうすればいいか分からない」と立ち止まってしまう方は少なくありません。
しかし、今の時代は「決めなくても動ける」ことが大きなポイントです。
放置すれば建物は劣化し、固定資産税や修繕費といった負担が増えていきます。
一方で、補助金制度を利用した改修や解体、自己負担ゼロの賃貸活用といった選択肢は、栃木の各市町村でも整備されています。
つまり「とりあえず相談して情報を整理する」だけでも、損を防ぐ第一歩になるのです。
相談は契約を意味しません。
むしろ、迷いを抱えたままの段階だからこそ、専門家に話す価値があります。
空き家の活用方法に正解はひとつではありません。
売却もあれば、賃貸や地域での利用もあります。
大切なのは、自分や家族にとって納得できる形を見つけることです。
迷い続けて放置するのが一番の損失。
まずは「話して整理する」ことから始めてみませんか。
その一歩が、空き家を守り、未来の安心へとつながっていきます。
この記事の監修者

高等学校を卒業後、東京トヨペットに3年間勤務。その後、「お客様の気持ちに寄り添った工事をしたい」という思いから独立をし、1989年にサワ建工株式会社を設立。空き家事業だけではなく、新築工事やリフォーム、不動産業など、人が安心して暮らせる「住」を専門に約30年間、東京・埼玉・千葉を中心に地域に根付いたサービスを展開している。東京都の空き家問題に本格的に取り組むべく、2021年から「あき家ZERO」事業を開始。空き家を何とかしたい、活用したいと考えている人へサービスを提供している。